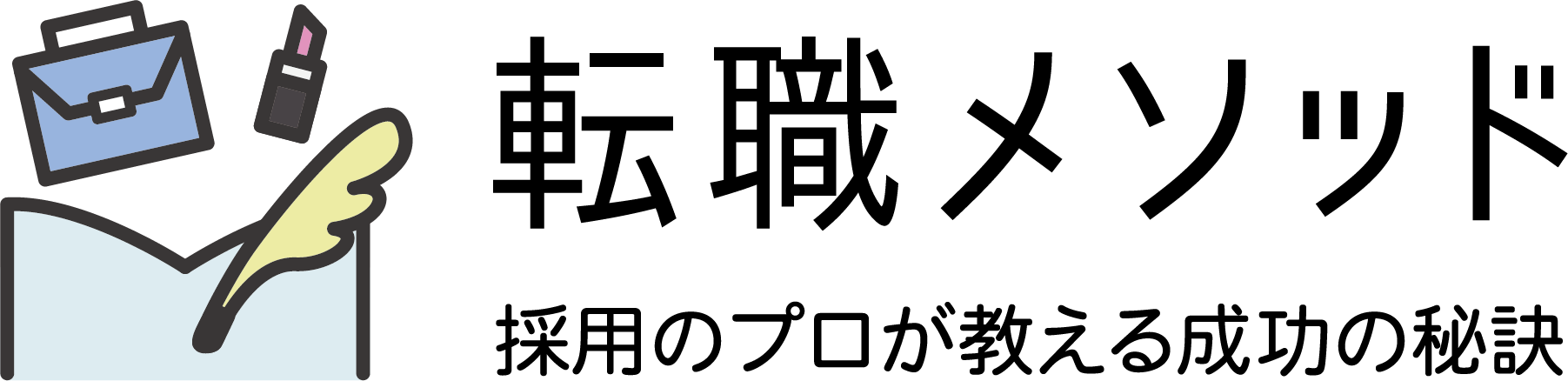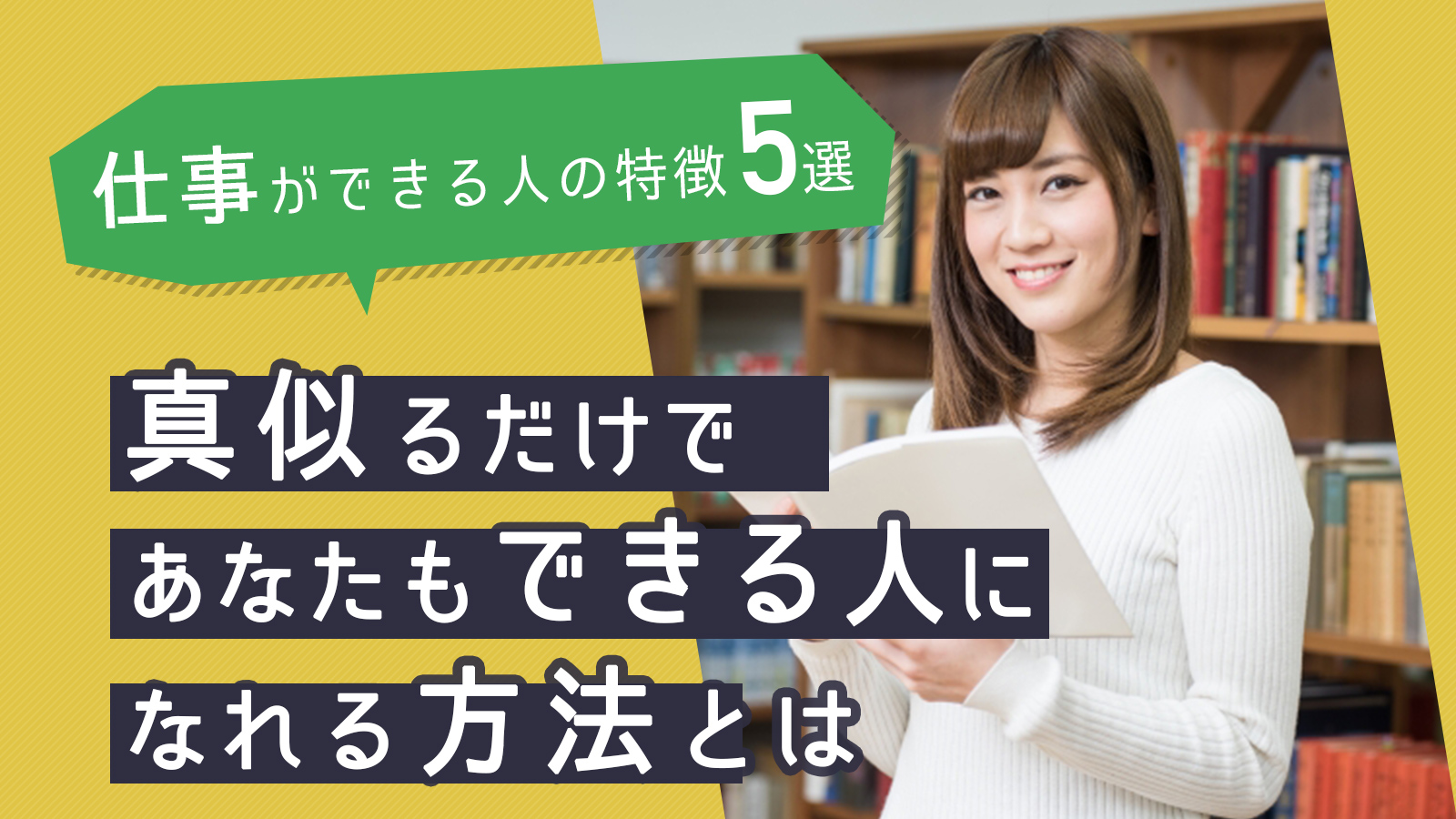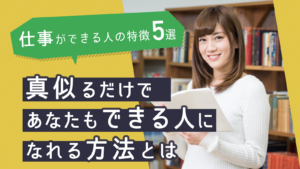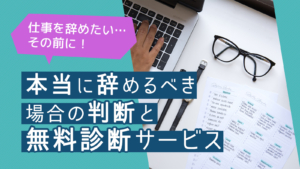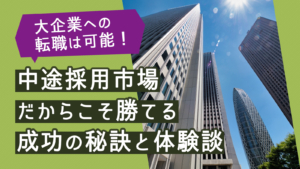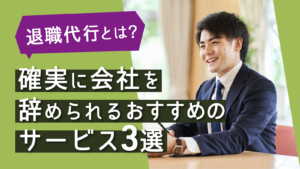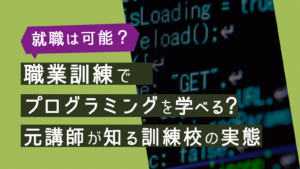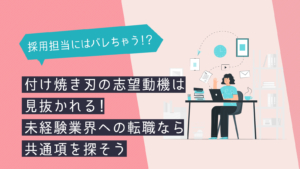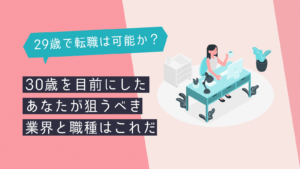あの人は仕事ができる…!と、バリバリ仕事をこなす姿を誰しも見かけるでしょう。
先輩ならまだしも、同期でも仕事ができる人は一目置かれる存在。いつの間にか差が大きく開いてしまい、焦ってしまうこともあります。
「同期のはずなのにおかしい…」「きっと何かコツがあるはず…!」そう思う方もいらっしゃいますよね。もし真似るだけであなたも仕事ができるようになるなら、ぜひ取り入れたいはずです。
実際に自身で転職を3回経験し、また上場企業で採用担当として年間で書類選考3000件、面接500人を見てきた筆者がこれらの疑問について回答します!
できるだけ具体的に真似ができるものをまとめました。仕事で一目置かれる存在になるためにも、ぜひチェックしてみましょう。
この記事を読むとこんなメリットがあります!
- 仕事ができる人の考え方を読み取れるようになる。
- 仕事ができる人の習慣を知り、自分も実践できる。
- コツの先にある仕事の本質を得られ、どんな業種にも対応できるようになる。
そもそも仕事ができる人とは?まずは仕事ができる意味を知っておこう!
そもそも仕事ができる人とは、どういう方を指すのでしょうか?仕事ができる人は一定の項目に優れています。
- 判断力に優れている
- とにかくスピーディーにこなす
- 結果を出すことに特化している
- 指示待ちではなく自ら行動する
この記事では、特に汎用性の高い上記4項目について解説していきます。
判断力に優れている
仕事に優れている人は、とにかく判断力が的確です。
例えば上司が離席している際、クライアントからクレームの電話があったとします。
内容もよくわからず、一方的かつ理不尽な内容に感じるかもしれません。
しかし判断力に優れている方なら、以下のような思考で考えます。
もしこのまま上司へ言伝をしても、相手の怒りは収まらないだろう
すぐにつなぐこともできないし、相手はもどかしさを覚えるはず
ここで(不快な気持ちにさせたことに対する)謝罪をして一次対応をし、詳細な内容も聞いて伝えておこう
そうすれば上司もすぐに対応ができて、相手も怒りが軽減されるはず
上記のように現在の事象と未来の予測を比較し、最善で合理的な判断が瞬時に下せます。
もちろん最初から判断力に優れている人はあまりいません。
少しずつ合理的な判断を下せるような習慣が身についているため、どんな状況下でも最適な判断が下せるようになるのです。
とにかくスピーディーにこなす
仕事ができる人は、とにかくスピーディーに物事をこなします。このスピード感は、全体像を把握する力が重要です。
そのためなんでもかんでも、早ければ良いというわけではありません。
優先順位を踏まえた上で、すべての実行スピードが早い。もしくはそう見える立ち回りをしています。
例えば期日が決まっている仕事があったとしましょう。仕事ができる人は全体像を把握しているため、前倒しでタスクを消化していきます。
やるべきことが明確であるなら、積極的にタスクを消化するほうが効率は良いからです。あとから修正の依頼が出ても、早めに提示しておけば余裕を持って取り組めます。
しかし仕事ができない人は目算を見誤り、期日ギリギリに成果を提出してしまうのです。
結果を出すことに特化している
単純に仕事ができる人は、求められる結果や成果を出すことに特化しています。
この能力は相手が求められる期待値を正確に読み取るほか、結果を出すための工夫をしているかどうかが重要です。
まず目標をなんとしてでも達成したい。そのためには何をどうしたらいいか、常に考え続けます。
飽くなき探究心から、少しでも進捗が悪い取り組みはすぐに除外するのも特徴の1つです。
例えば売上の達成がこのままでは困難と知れば、採算が合わない既存顧客の対応ではなく、新規顧客の開拓に切り替えるといった手段を取ります。
結果を出すためには日々の小さな数字の動きも観察し、ゴールと比較して概算を立てるのが大切です。
少しでも動きが悪いならなんらかの工夫をして、結果をなんとしてでも出そうとします。
指示待ちではなく自ら行動する
仕事ができる人は、「こうしたらもっと良くなるかもしれない」という提案を積極的に行えます。
普段使っているフォーマットの精度が低いため、自身で改善して上司に提案してみる…といったものです。
ただし仕事ができない人の場合、提案をすると逆に反感を覚えさせてしまう場合もあります。
相手との信頼性や業務の全体像を把握していないため、上司に受け入れられないこともあるのです。
仕事ができる人はそういった状況でも相手をしっかり立て、嫌な気持ちにさせないよう提案します。
どの業界、どの分野でも日々改善をすることは山程あるでしょう。指示待ちでしか動けない人は、仕事の効率が上げられません。
常に疑問を持ち、どうしたらこの業務がよりやりやすくなるだろう?と考えるのが重要です。
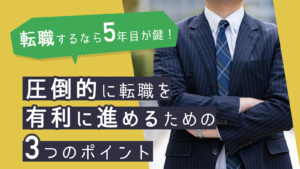
仕事ができる人は普段から習慣や考え方で差をつけている!
仕事ができる人は、最初から仕事ができていたわけではありません。
少しずつ習慣や考え方で向上し、他者が驚くような結果を出していくのです。
そのため仕事ができる人を知るには、そういう方々の習慣や考え方も知る必要があるでしょう。
自分を大きく評価しない
仕事ができる人は、自分を大きく評価しません。
例えば上司から怒られたとして、自分を高く評価する人とそうじゃない人はどういう思いを抱くでしょうか。
自分を高く評価する人は、「なんて理不尽なんだ!こちらのやり方が合っているのに」と過ちを認めないでしょう。
しかし自分を過大評価しない人だと、「もしかしたらやり方が間違っているかもしれない。見直す必要があるな」と冷静に指摘を受け入れられます。
また過大評価をしない人は、褒められたり表彰されたりしても慢心をしません。「偶然良い結果が重なった」と判断し、手を緩めることがないのです。
評価を高めてしまうと、「自分はすごい」という慢心のせいでどこかに油断が生じてしまいます。
切り替えが早く改善点を活かせられる
仕事ができない人ほど、うまく切り替えができずに業務へ支障をきたしてしまいます。
どうしても怒られたり失敗してしまったりすると、気分が落ち込んでしまうのは仕方ないでしょう。
しかし仕事ができる人は、その失敗の経験を活かして「次は絶対失敗しないようにしよう!」と、対策を万全に整えます。
結果として同じミスをしないよう行動するため、失敗のたびに成長していくのです。
この切替が遅いと、どうしても同じミスをしやすい状態になります。
不安定であれば普段できている業務でさえ、うっかりミスをしてしまう可能性も高まるでしょう。
またミスが続くと、どんどん自己嫌悪していくトラップにもかかってしまいます。
切り替えた上で対策を整えられるかどうか、その積み重ねができる人とできない人の差は大きいです。
隙間時間を有効に使っている
できる人は、少しでも空いた時間を使って効率よくタスクをこなします。
どんなに激務な仕事内容でも、隙間の時間は確実に存在するはずです。この時間を使い、細かいタスクを効率よく片付けています。
とくに細かいタスクは、塵も積もれば山となりやすいです。気づけば重要度の高いタスクと並んで負担を押し上げるため、重要度が低くても侮れません。
とはいえメイン業務の時間を使ってまでやるほど、重要度が高い案件でもないでしょう。
優先順位が低くても、細かいタスクは処理できるうちにやっておくのがベストです。
しかし仕事ができない人は、そういった細かいタスクを放置してしまいがち。会議前の空いた時間でもメールチェックをせず、後回しにしてしまうのです。
時間辺りの効率を上げていれば、人よりも多くのタスクをこなせます。
仕事ができる人に近づく!すぐにでも真似ができる方法を5つ厳選!
では実際に、仕事ができる人に近づくコツをお伝えしていきます。
ただしこのコツはあくまで本質をつかみやすくするための、1つの手段です。
ご紹介する方法を実践しながら、状況に合った最適なやり方へとカスタマイズしていってください。
1.ToDoリストを活用して全体の把握と優先順位をつける
まずToDoリストを活用し、やるべきことの全体像を把握しましょう。
Windowsを使っている方でしたら、付箋機能が便利です。この機能で複数のパソコンとスマホも連動できるため、常にタスクを確認できます。
そしてToDoリストにやるべきことを書き出したら、優先順位をつけていきましょう。
期日が決まっているものなら期日を書くと良いですね。今日中にやるべきことは最上位に掲載しておきます。
こうすることで全体の把握が行えて、「今は余裕があるから先に進めておこう」と思えるはずです。
またタスクをこなしたあとは、すぐに該当の項目をリストから消してみてください。
実際に書き出したものを消していく行為は、意外と爽快な気持ちになります。
最初は当日のリストを綺麗にするため、慣れてくれば前倒しで消していくためと、目的と行動が一致しやすいです。
2.テンプレートやツールを活用して作業を効率化する
何度も同じ作業や似た業務を行う場合、テンプレートを作成しておくと便利です。
ほかにも自分なりのマニュアルを作成し、情報を整理してみましょう。
このマニュアル化は口頭で報告業務を行う際にも有効です。予め決められたマニュアルで報告事項を作っておき、その事項に沿って報告していきます。
またツールを活用するのも良いです。中には外部のツールが導入できない場合もあるでしょう。
しかし筆者は以前、注文の受注数を保存するシートを電子化した経験があります。
ずっと手書きで使われていたため、全く同じものをExcelで作成。計算式も入れて自動で入力できるようにし、人為ミスと工数を減らしました。
ツールと言っても優れたものを導入する必要はありません。身の回りのもので改善できるものがあれば、積極的に活用してみてください。
可能であれば上司に進言し、ツールの導入をしてみても良いです。
3.完璧主義者をやめて柔軟に対応する
完璧に業務をこなそうとせず、注力すべきポイントにだけこだわってみてください。
仕事が遅い人は多くの場合、完璧主義者になっている傾向があると感じます。
「とにかく任された仕事は完璧にこなさないといけない」と、こだわりを追求している方が多いです。
もちろん上司によっては口うるさく指摘してくることもあり、避けるために時間を費やしていることもあります。
しかし一番重要なのは「クオリティを上げること」です。質を高めるなら、成果とフィードバックの回数をこなすしかありません。
全体像を把握した上で、注力すべきポイントにだけ絞って成果を提出しましょう。
そうすれば期日よりも早い提出ができるため、早期にフィードバックを受けられます。
期日ギリギリで提出した場合、やり直しが発生すると全体の進捗にも影響を及ぼすかもしれません。
4.常に比較するクセをつけて深堀りをする
常に比較するクセをつけてみてください。例えば最高の状態と、最悪の想定です。
最高の状態であれば、もう求めるものは何もありません。まさに求めている最高の結果が出ている状態です。
しかし最悪の想定は、できるだけ避けたい事態ですよね。この事態を避けるために何をどうしたらいいか考えます。
その上で、現在の自分が置かれている状況を比較してみてください。客観的に見て、自分がどういう想定の位置にいるかわかるはずです。
比較をすると客観性が見えてきて、次に取るべき行動も把握しやすくなります。
とくに最悪の想定はよくしておくべきです。同じ作業1つ取っても、最高の状態なら何もしなくて良いでしょう。しかし最悪の状態はクレームへとつながります。
避けるべきは最悪の事態です。比較することで、逆算ができるようになります。
5.スピードを求めるのは一番最後!余裕ができてから
よく仕事ができる人はスピード感があると聞き、とにかくスピーディーにこなそうとしてしまう方がいます。
しかしスピードを求めるのは最後にしましょう。なぜなら仕事が遅い人は、スピードではなく余裕がないからです。
仕事ができる人は常に前倒しでタスクをこなすため、新しく入る業務もすぐにこなせます。
つまり現状タスクの全体像を把握していないなら、ただ闇雲にスピード感を高めても疲れてしまうだけです。
まずは全体像を把握して少しずつ余裕を作ってみましょう。余裕が出てくれば、自然とスピード感が出てきますよ。
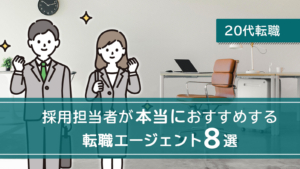
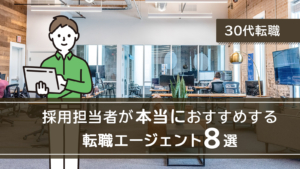
まとめ
仕事のできる人とそうじゃない人の違いは、本質を掴めているかどうかです。
基本的に価値は信頼のやり取りで生まれ、価値に正しく答えられていれば信頼を得られます。
「相手は何を求めているんだろう?」「自分がどういう行動をしたら価値を感じるのか」この考え方を意識していれば、自然と仕事のできる人に近づくはずです。
しかし本質をすぐにつかめるなら、苦労しませんよね。この記事ではそんな本質を掴むための、すぐに活かせる5つのコツを紹介しました。
少しでもあなたの仕事術が正しく価値を生み出せるよう、お祈りしております。