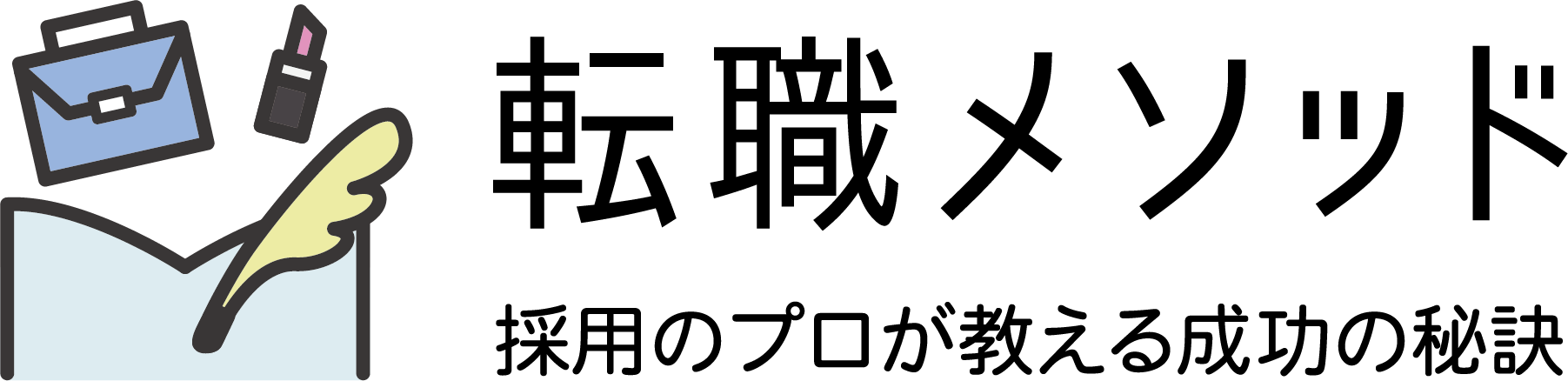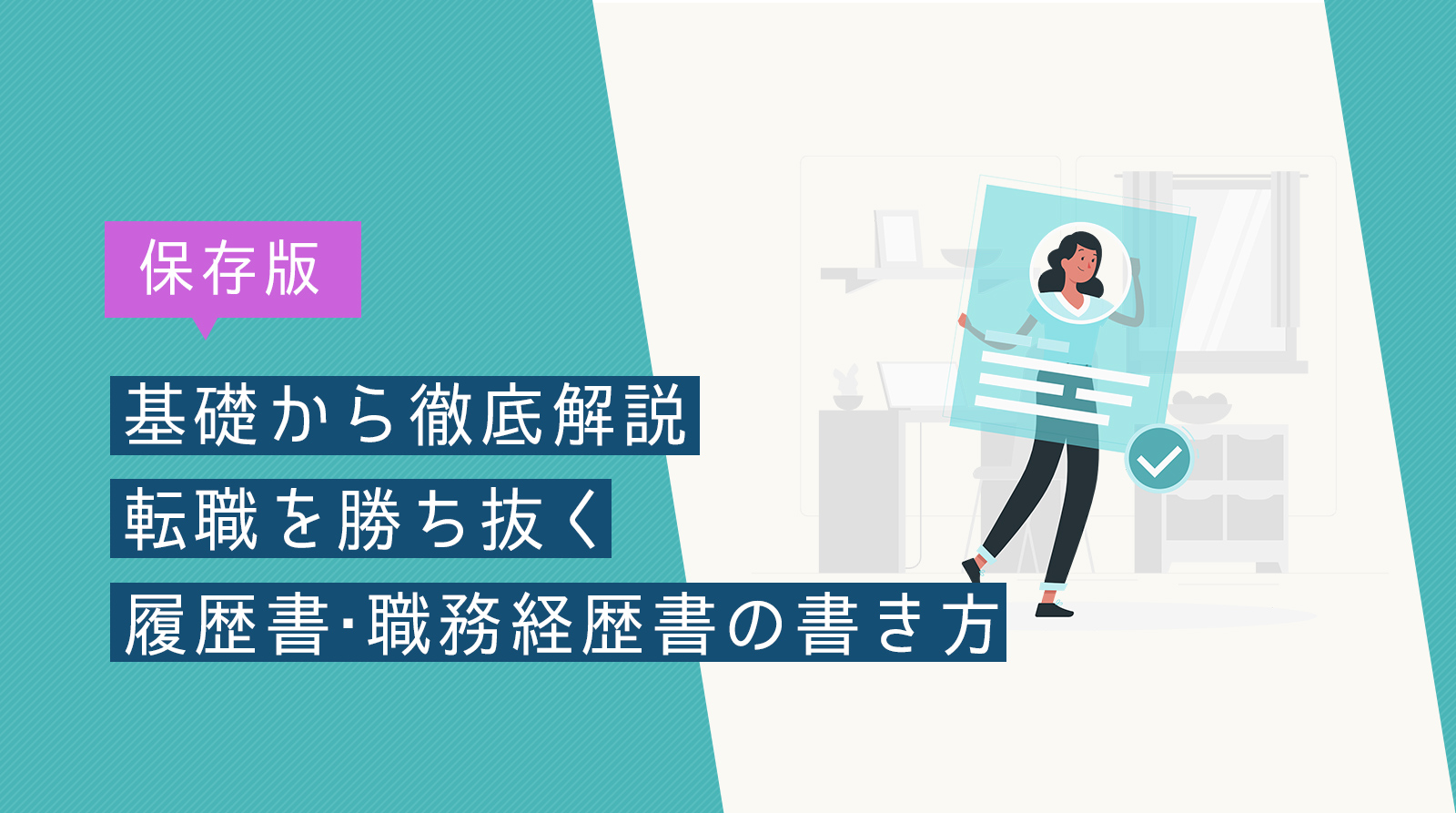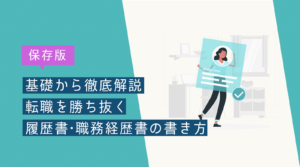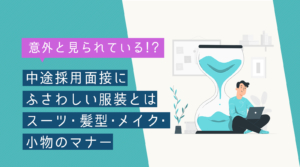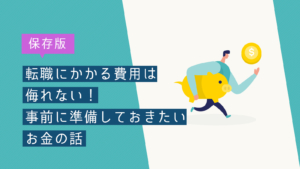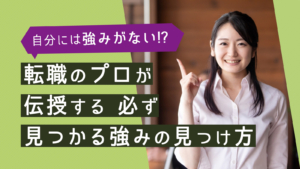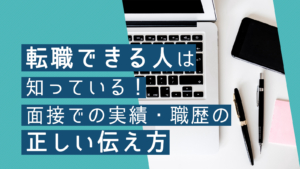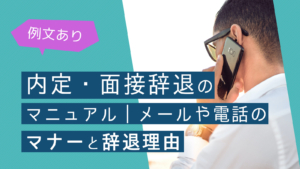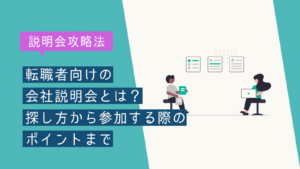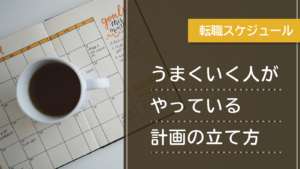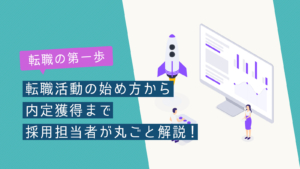魅力的な履歴書・職務経歴書は書き方次第!基本を押さえるだけで応募書類の質は、ぐっと上がります。自分の経験やスキルが十分に伝わる履歴書・職務経歴書の書き方を知り、「会ってみたい」「もっと知りたい」と思ってもらえる書類作りを意識しましょう。
転職活動のほとんどの場合、履歴書とともに職務経歴書の提出が求められます。履歴書と職務経歴書の違いについても徹底解説します。
書類選考を通過しない限り、転職は成立しません。採用担当者は応募書類のどこを見ているのか、見落とされない履歴書作りの注意点も合わせてご紹介します。
履歴書と職務経歴書の基本を理解しよう
多くの会社では「履歴書」と「職務経歴書」の両方の提出を求められます。この二つにはそれぞれに重要な役割があり、転職活動における職務経歴書はあなたを売り込むプレゼンテーション資料になります。これらの書類の質を上げることで転職活動を有利に進めましょう。
履歴書と職務経歴書の違い
履歴書には最低限必要な情報が集約されており、基本事項はほぼ統一されています。「氏名・住所」や「略歴・資格」などある程度フォーマットが出来ている書類であり、あなたの「プロフィールを確認する書類」となります。
一方、職務経歴書には決められた形式が無く、自由に作成することができる書類です。「そんな書類がなぜ必要なの?」と思われるかもしれませんが、職務経歴書は「業務経験」や「仕事に対するスキル」を確認するために用いられています。それぞれに重要や役割があり転職活動には欠かせない書類なのです。
履歴書は減点方式、職務経歴書は加点方式で見ているわね。
履歴書の種類
市販の履歴書には、たくさんの種類があり悩まれる方も多いのではないでしょうか?
形式は大きく分けて、JIS規格と呼ばれる国際基準のA4(見開きA3)と、一般的に用いられる日本規格のB5(見開きB4)の2種類があります。企業からの指定が無い場合は基本的にはどちらを使用しても問題はありません。
ただし、外資系の企業に応募する場合には、国際基準のA4サイズが望ましいでしょう。
そのほかにも、「転職向け」「一般向け」「パート・アルバイト向け」「新卒向け」などがあり、それぞれの履歴書によって特徴があります。
■JIS規格
外資系企業や、中途採用する企業が履歴書の指定してくる場合はJIS規格が多いです。一般向けに比べ学歴や職歴の記載欄が多く設けられており、志望動機や自己アピール欄がまとめられているのが特徴です。
たとえ履歴書の指定が無い場合でも外資系企業への応募の際は、こちらを使用しましょう。
■転職向け
転職者向けの履歴書では、経歴や実務経験が重視されるため、あらかじめ経歴欄が多めに設定されています。もし経歴や実務経験が浅くアピールが難しい場合は、転職向けの履歴書ではなく一般向けの履歴書を使うと良いでしょう。
■一般向け
転職者はもちろん、新卒、パート・アルバイトへの応募にも使用できるオールマイティタイプになります。自己アピール欄が多く設定されているので、そちらに重点をおきたい場合にはおすすめです。
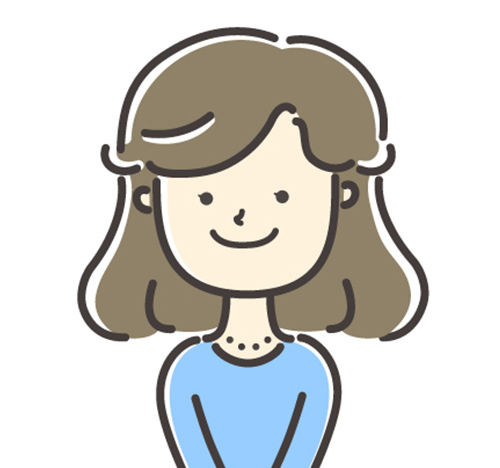
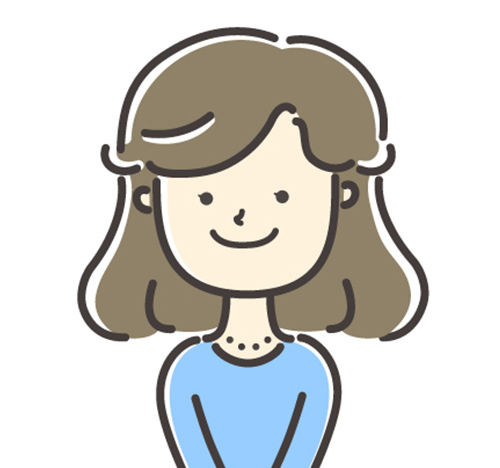
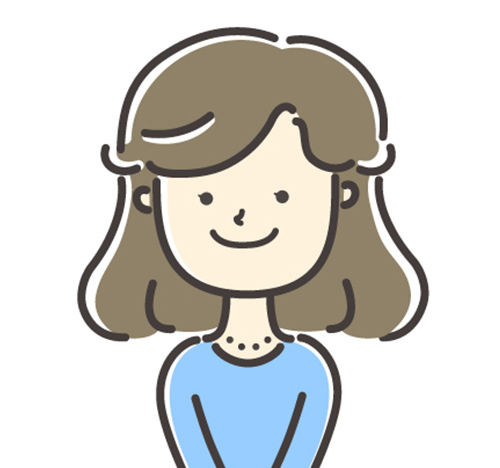
履歴書の種類で落とされることはないけど、
迷ったら「A4サイズ/転職向け」を選ぶと間違いなし!
履歴書作成 ポイントを押さえミスを防ごう
履歴書を書く際の基本的注意点を理解し、初歩的ミスを無くしましょう。
POINT1【誤字・脱字、略語に注意!】
経歴記入の際に、卒業や入社年度などの間違いに注意しましょう。勘違いによる記入間違いであっても、履歴書ではあってはいけないことです。数多くの履歴書を見てきている採用担当者は小さな誤字・脱字であってもすぐ気づきます。事前にしっかり確認し偽りのない内容を書くことが大切です。
また、「(株)」のような略字は使わず、「株式会社」と正式名称で書きましょう。学校名も同様に、「都立」は「東京都立」、「高校」は「高等学校」と正式名称で書きます。
POINT2【年号は西暦・和暦どちらかで統一する!】
西暦・和暦どちらで記載しても問題はありませんが、必ず統一しましょう。多い事例として、生年月日は和暦で記入し、学歴・職歴欄は西暦で記入してしまうことです。時系列がわかりにくくマイナスイメージに繋がってしまうため必ず統一しましょう。
さらに、「令和」は「R」、「平成」は「H」、「昭和」は「S」と略称を使用しがちですが、アルファベット略称は使用せず正式な表記で記入しましょう。履歴書は正式な書類ですので、略称は望ましくありません。
POINT3【消せるボールペンは使用不可!】
鉛筆やシャープペンはもちろんですが、消せるボールペンの使用もやめましょう。一文字でも間違えてしまうと最初から書き直しになってしまい時間もかかり面倒ではありますが、必ず油性インクのボールペンで書きましょう。
消せるボールペンで作成した書類は、他の人が改ざん・修正可能な書類となり信用性に欠けます。慣れない履歴書を記入していく上で間違いは付きものなので、あらかじめ下書き用の履歴書を一枚作成し、それを見ながら正書するように書いていくとよいでしょう。
また、修正液や修正テープの使用も絶対にだめです。たった一箇所であっても履歴書にとっては大きなマイナス点となります。
POINT4【空白は絶対にNG!】
転職活動において、履歴書の書類選考は第一関門です。その大切な書類に空白があっては不利になるでしょう。採用担当者は履歴書を見て応募者を判断します。いかに採用担当者の目に留まるか、好印象を与えるかが鍵となり、今後の選考に大きく関わっていくものになります。
免許・資格欄は、記入できるものが無い場合は書く必要はありませんが、「志望動機」「自己㏚」「本人希望欄」などの各欄はあなたを売り込むために設けられたスペースです。そのスペースを有効活用し最大限のアピールをしましょう。
POINT 5【パソコン作成も可能!】
応募先より履歴書の手書き指定がない場合は、パソコンでの作成も可能です。履歴書のフォーマットをダウンロードしパソコン上で必要事項を入力しプリントアウトするといったものです。転職活動の際は複数枚の履歴書を作成するため、繰り返し印刷できるパソコン作成を選ぶ人も増えています。
一方、パソコンでは味気ない印象になり「採用担当者の印象に残らないのではないか」と思い、一枚一枚手書きで作成している方も多いです。
どちらが良いということはありませんが、強いて言えば「文字から人物を想像する」「応募者の性格を読み取る」という採用担当者は多いため、履歴書は手書きで記入し職務経歴書はパソコンで作成するケースが一般的になっています。
ただし、パソコン業務中心の企業やIT企業への応募の際は、あえてパソコンで作成することにより、スキル証明ができ好印象を与えるでしょう。
また、癖字が強い方や文字に自信がない方はパソコン作成を選ぶとよいかもしれません。「読みづらい」「何て書いてあるかわからない」という印象を回避できます。
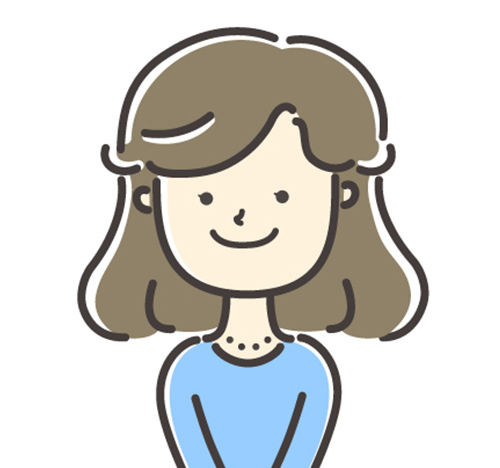
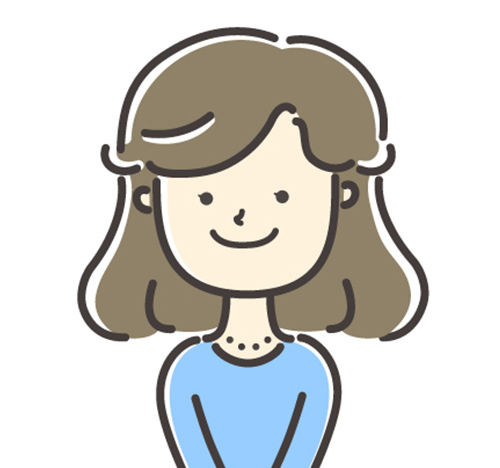
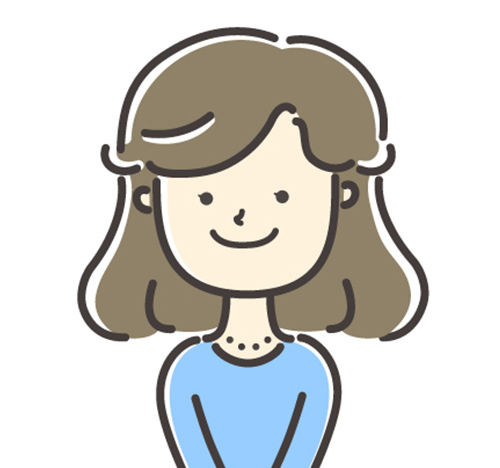
一昔前とは違って、今はパソコンで作った履歴書も増えているわ。
私がいた会社では選考の合否に影響することはなかったの。
履歴書の記入方法
転職時に適した履歴書の記入方法や注意点をしっかり押さえ、充実した履歴書を作成することが重要です。また、応募する企業にあった視点で記入することを心がけましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日付 | 投函日もしくはメール送信日、持参する場合は持参日の日付を記入 |
| 氏名 | 苗字と名前の間はスペースを空け読みやすく |
| 年齢 | 提出日時点の年齢 |
| 電話番号 | 自宅固定電話が無い場合は、携帯電話のみを記入 |
| メールアドレス | 合否連絡や確認連絡が迅速に取れる携帯アドレスを記入 |
| 学歴・職歴 | 在籍したすべての会社を記入 |
| 免許・資格 | 取得年月日順に記入、ない場合は「特になし」と記入 |
| 志望動機 | その企業を選んだ理由と、入社後の目標や実現させたいこと |
| 自己PR | 今までの実績と自分の強み・スキルのアピール |
| 本人希望 | 特にない場合は「貴社の規定に従います。」と記入 |
基本情報欄の書き方
日付・氏名・住所などの基本項目は、旧字ではなく戸籍に登録されている正しい文字で正確に記入し、数字は「1、2、3」などのアラビア数字を使用します。印鑑はシャチハタ以外の朱肉を使う認印を使用しましょう。
学歴・職歴欄の書き方
一行目中央に「学歴」と記入します。「学」と「歴」の間はスペースを空け文字の間隔を整え記入しましょう。転職時の学歴は高校入学以降、もしくは最終学歴からの記載が一般的です。略字は使わず、「都立」は「東京都立」、「高校」は「高等学校」と正式名称で書きます。
一行空け、学歴同様に「職歴」と記入します。職歴は今まで在籍したすべての会社を記載しましょう。「会社名」に続き「配属部署」「業務内容」を具体的に記載することが大切です。また、同一企業にて異動・昇格した場合もすべて記載しましょう。
【 例 】
| 2010年4月 | 株式会社〇〇 入社 通信事業部配属顧客情報管理・データ入力を行う |
| 2013年10月 | 株式会社〇〇関東支社へ異動顧客情報管理責任者に昇格 |
| 2016年9月 | 株式会社〇〇 一身上の都合により退職 |
| 2016年10月 | △△株式会社 入社 営業部配属企業用印刷機の新規開拓業務を行う |
| 現在に至る | |
以上 |
免許・資格欄の書き方
保有免許から書き、次に保有資格を記入します。「自動車免許」ではなく、「普通自動車第一種運転免許」と正式名称で書きましょう。もし、資格習得に向け現在勉強中、結果待ちという場合であっても、「習得見込み」と書くことはやめましょう。応募する企業に役立つ資格でアピールしたいときは、自己PR欄を活用し勉強中であることを伝えると良いでしょう。
志望動機欄の書き方
転職活動において採用担当者が最も重視する項目が志望動機欄でしょう。「会社が求めている人材か」「会社に貢献してくれるのか」という部分に重点をおき応募者を見極めています。どんなに熱意があっても、企業が求めているニーズにあっていないと採用されません。
- 会社を選んだ理由
- なぜ他社ではだめなのか
- どのような経験を活かせるのか
- どう貢献できるのか
- 入社後の目標
志望動機欄は、「会社に対してのこだわり」をアピールする項目です。
その企業の情報を理解し、その上で自分の経験や実績をどう活かせるか、スキルや強みを踏まえアピールする必要があります。
自己PR欄の書き方
長く勤めて、会社に貢献してもらえなくては採用する意味はありません。採用担当者は「仕事に対する姿勢」を知りたいのです。
これまで積んできた「経験・スキル・成果」が、これからどのように活かせるのかをイメージさせることが重要になります。
- 挑戦心やチャレンジ精神
- 学ぶ姿勢
- 実行力
- 柔軟性
- 成長意欲
- 正確性
自己PR欄は、「会社へ貢献できる度合い」をアピールする項目です。
「今まで何をやってきたか」「何ができるか」を具体的なエピソードを交えて書くことにより、自分の魅力を伝えることができるでしょう。
本人希望欄の書き方
なんでも書きたいことを書いて良い欄ではありません。どうしても譲れない条件があり、先に伝える必要がある場合のみ記入しましょう。本人希望欄に書かれたことは「入社条件」と判断します。給料や休日条件などの待遇面は、面接の場で交渉することも可能です。まずは書類選考を通過する必要があるため、「会ってみよう」と思わせることが大切です。
在職中などで電話に出られる時間が限られている場合は、連絡がつく時間帯を本人希望欄で伝えておくと良いでしょう。
また、希望職種がある場合もあらかじめ記入しておきましょう。
【 例 】
- 在職中のため、平日の9時から18時は電話に出ることができません。
- 平日は17時以降にご連絡いただけると幸いです。
- 可能な限り早めに折り返しご連絡を差し上げます。
- 営業職を希望いたします。
- 現職の引継ぎの関係上、就業可能になるのは〇月以降となります。
特にない場合は、「貴社の規定に従います。」と書くのが一般的です。
職務経歴書はプレゼン資料
職務経歴書は決まった形式がなく自由に作成できる分、「資料作成能力」も見られています。出来る限り簡潔にわかりやすく伝え、読みやすさ・見やすさに重点をおき作成しましょう。
職務経歴書は自分を売り込むための「プレゼン資料」です。このプレゼンを魅力的なものにできるかどうかが鍵になります。
今までどんな仕事をしてきたか=これからどんな仕事をしてもらえるか」
「このような成果を残せた=今後どんな成果を残してもらえるのか」
と変換し考えます。応募先企業から「働いてもらいたい」と思ってもらうことが最終目標なのです。
転職活動では、履歴書よりも職務経歴書が圧倒的に重要!
職務経歴書は、履歴書で伝えることができなかった、これまでの実績やスキルを詳しく具体的な内容で書くことができます。しかし、書きたいことをただ書けばよいわけではなく、企業側が見たい内容を書くことが大切です。
的外れなアピールばかりをしていても意味がありません。企業が求める情報をプレゼンし、「もっと知りたい」「働いてもらいたい」と思われる職務経歴書を作りあげることが重要です。
職務経歴書で見られているポイント
- 転職目的がはっきりしているか
- 求めている条件を満たしているか
- 自分の強みを自覚しているか
- 過去のキャリアを元に、自社で活躍できそうか(再現性)
- プレゼン能力があるか
採用担当者が見ているポイントを理解し、的にあったプレゼン資料を作成しましょう。
この中で最も大切なのは、
「過去のキャリアを元に、自社で活躍できそうか(再現性)」ね。
求人の内容をよく読んで、具体的にシミュレーションしてみましょう。
職務経歴書は、パソコンがおすすめ
A4用紙1~2枚、多くても3枚程度にまとめます。「プレゼン資料」と呼ばれるだけあり履歴書に比べ情報量が多くなります。そのため手書きでは読みづらい印象を与えてしまう可能性があり、デザイン性や効率化を考えるとパソコン作成することをおすすめします。
ただし、企業によってはパソコンスキルの判断材料にもなり得るため、フォントの大きさ、文字のバランス、罫線・枠の統一などに気を付けましょう。分かりやすく簡潔に見えるよう、改行や箇条書きなどを使い整えることが必要です。
職務経歴書 ポイントを押さえ印象を良くしよう
採用担当者に「読もう」と思ってもらうためには、まずは第一印象を良くする必要があります。記録や経歴を羅列するのではなく、読み手側の知りたい情報をわかりやすいレイアウトでまとめることが重要です。
- 見やすいレイアウト
- 読みやすい文面
- 簡潔にわかりやすく
- 具体的なエピソード
単なる文章ではなく、自分だけのオリジナル資料を作り上げるつもりで作成しましょう。
職務経歴書の作成方法
最低限必要な項目を理解し、詰め込みすぎない職務経歴書を作成しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 職務要約 | 冒頭に職務経歴の「まとめ」を記入 |
| 職務経歴 | 今までの仕事内容を記入 |
| 活かせるスキル・知識 | 業務スキルやビジネススキルを記入 |
| 資格・免許 | 保有している資格・免許を記入 |
| 自己PR | 自身の強みや貢献度を記入 |
職務要約の書き方
今までの職務のまとめを冒頭に記載します。一般的には3行程度(100~200文字程度)とされており「この先に何が書いてあるのか」を伝える重要な部分になります。
採用担当者はまずここを読み、詳しい職務経歴を読むか読まないかの判断をしているといっても過言ではないでしょう。応募先の企業との接点を見つけて、採用担当者の興味を引き寄せる書き出しが求められます。
職務経歴の書き方
今までの「在籍年月」「企業名」「事業内容」「資本金」「従業員数」「売上高」などの会社の情報と、携わってきた「職務内容」を詳細に書き出します。未経験者が見ても伝わる内容で具体的に書きましょう。



ただ職務内容を羅列するだけではダメ!
応募職種で活かせそうな内容に重点を置いて書くといいわよ。
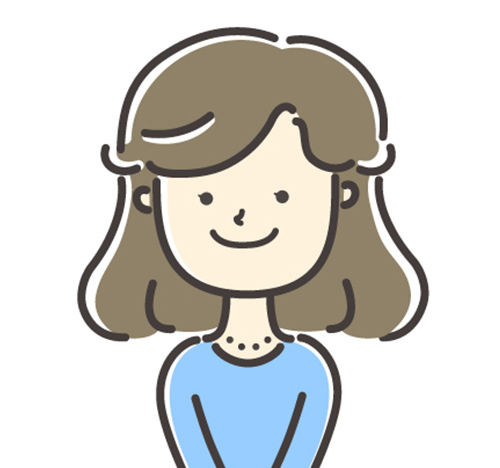
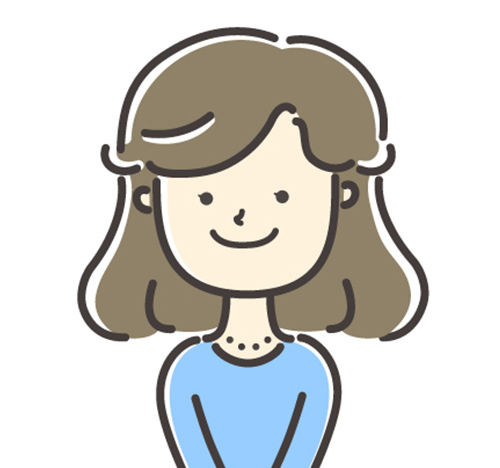
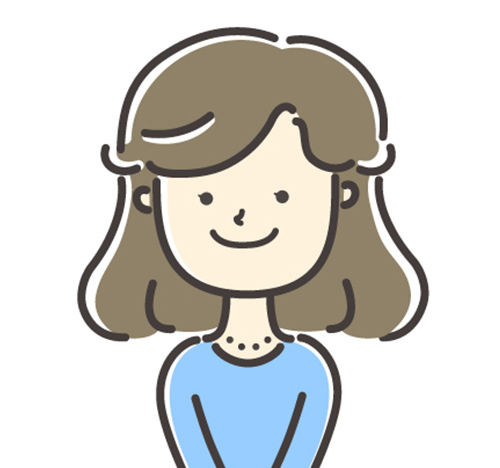
実際に取り組んだ際の「考え方」「行動」「結果」が簡潔に書いてあると、入社後の活躍が想像しやすいわ。
活かせるスキル・知識の書き方
これまでの経験で身につけたスキルで、応募先の企業で活かせるものをピックアップし書きましょう。採用担当者がイメージしやすいよう、使用場面を具体的に表すと効果的です。



求人内容に関係ないものが書いてあっても仕方がないのよね…。
「どのように活かせるのか」について知りたいの。
資格・免許の書き方
履歴書にも記載してあるので、補足する点を書くと良いでしょう。保有資格が実際にどのように役立っているかを書き出しましょう。
自己PRの書き方
自分自身の強みを伝え、入社後にどのように活かせるのか、また具体的な貢献度を交えアピールしましょう。履歴書の自己PRと職務経歴書の自己PRが一致してないということが無いように注意しましょう。
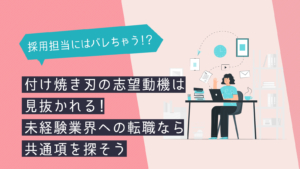
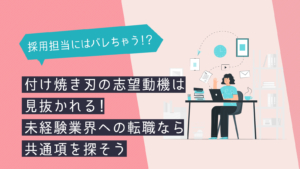
職務経歴書のテンプレートを使用しよう
レイアウトまでは考えられないという方は、テンプレートを使用するとよいでしょう。決まった形式が無い分、数多くのテンプレートがあるので自分のキャリアに合ったテンプレートを選びましょう。
「編年体式」「逆編年体式」「キャリア式」などがありますが、迷ったら一般的な「編年体式」を使用することをおすすめします。
編年体式とは?
一般的に使われているタイプで、時系列で経歴紹介をする形式です。今までの経験を活かし転職する方に使いやすい形式です。
逆編年体式とは?
直近の仕事内容から書き出す形式で、前職を強くアピールしたい方に適した形式になります。
キャリア式とは?
転職回数が多くさまざまな分野を経験した方向けに、分野別にまとめて書く形式になります。
業界最大手の転職サイト「リクナビNEXT」では、「履歴書」「職務経歴書」のテンプレートがダウンロードできるようになっています。履歴書と職務経歴書を作成するのが面倒な方は、リクナビNEXTにレジュメ登録するのがお勧め!リクナビNEXTに、プロフィールや職務経歴などを入力すると、入力された内容に従って自動で履歴書と職務経歴書が作成され、Word形式でダウンロードすることができますよ。
応募する企業の分だけ、応募書類は必要になる
転職活動では複数の企業に応募するため、応募する企業の分だけ履歴書や職務経歴書が必要になります。それぞれに企業に合わせて志望動機や自己PRを記入しているため、間違った書類が混在しないよう注意が必要です。
封筒や証明写真も応募する企業分だけ必要になるので、余裕をもち揃えておきましょう。
また、せっかく書いた履歴書が汚れたり折れ曲がったりしないよう、クリアファイルに入れてから封筒に入れるとよいでしょう。綺麗な状態で送ることができ、常識がある人、配慮ができる人と認識してもらうことは大切なことです。
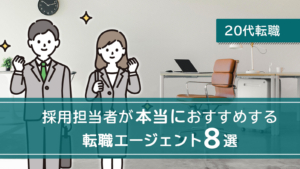
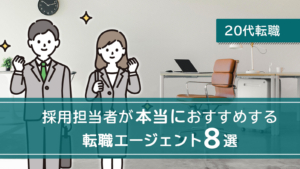
まとめ
職務経歴書において大切なのは「読ませる工夫」と「活かせる経験」です。どんなに優秀な人材であっても採用担当者に興味を持ってもらえなくては、面接のステージへは立てません。
本記事を参考に「履歴書」と「職務経歴書」の内容をしっかりと作り込んでみましょう。ポイントは、企業が求める人材に沿った資料作りです。「過去のキャリアを元に、自社で活躍できそうか(再現性)」についてしっかりと考えてくと良いですね。
抜かりない資料作りを経て、書類選考通過を目指しましょう!